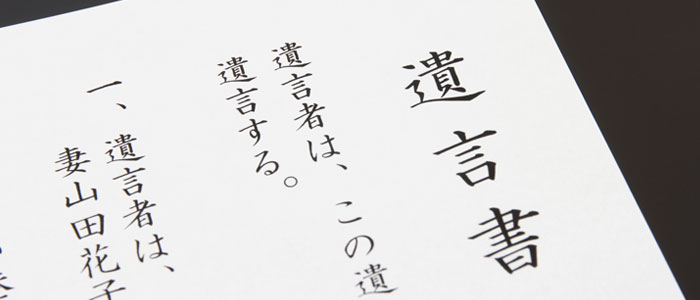
最高裁平成21年3月24日判決の解説
1 事案のご説明
(1) 甲さんは、その有する財産全部をYさんに相続させる旨の公正証書遺言(以下「本件遺言」といいます。)を作成しました。本件遺言は、Yさんの相続分を全部と指定し、その遺産分割の方法の指定として遺産全部の権利をYに移転する内容となっていました。その後、甲さんは亡くなりましたが、その法定相続人は、子であるXさんとYさんだけでした。
(2) 甲さんは、相続開始時において、積極財産として4億3231万7003円、消極財産として4億2483万2503円の各財産を有していました。本件遺言により、遺産全部の権利が相続開始時にYさんに承継されました。そこで、Xさんは、Yさんに対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示を行いました。
(3) Xさんは、甲さんの消極財産のうち可分債務については法定相続分に応じて当然に分割され、その2分の1をXさんが負担することになるから、Xさんの遺留分の侵害額の算定においては、積極財産4億3231万7003円から消極財産4億22483万2503円を差し引いた748万4500円の4分の1である187万1125円に、相続債務の2分の1に相当する2億1241万6252円を加算しなければならず、この算定方法によると、遺留分の侵害額は、2億1428万7377円になると主張しました。
これに対し、Yさんは、本件遺言によりYさんが相続債務を全て負担することになるから、Xさんの遺留分の侵害額の算定において遺留分の額に相続債務の額を加算することは許されず、遺留分侵害額は、甲の積極財産から消極財産を差し引いた748万4500円の4分の1である187万11125円になると主張しました。
2 判決要旨
最高裁平成21年3月24日判決は、以下のように述べて、遺留分侵害額の算定にあたり、法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することはできないと判示し、Xさんの主張を認めませんでした。
① 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、特段の事情のない限り、相続人間においては、当該相続人が相続債務を全て承継することになる。もっとも、遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者の関与なくされたものであるから、各相続人は、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなければならない。
② 遺留分侵害額の算定は、相続人間において、遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数学を算出するものであるから、遺留分の侵害の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ、これに応じた場合も、履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することは出来ず、相続債務を全て承継した相続人に対して求償し得るにとどまる。
コメント
上記判決は、簡単に言うと、「遺留分の問題は、あくまで相続人間の問題なのだから、被相続人の債権者から後日請求されるかもしれない債務の負担分については考慮しない。遺留分権利者が、後日、債権者に請求されて、支払わなければいけなくなった分は、プラス財産を全て相続した相続人に対し、後で請求すればよろしい。」との考えを明らかにしたといえるでしょう。
遺言書により他の相続人Aさんに全財産が承継されてしまったにも関わらず、Bさんは債権者から法定相続分に従った債務の弁済を請求される可能性が残ってしまい、その上、BさんからAさんに遺留分減殺請求するにあたっての遺留分の計算にあたっては当該弁済の分は考慮してもらえない、というのは、遺留分権利者Bさんにとっては踏んだり蹴ったりのような気がされるかもしれません。
しかし、遺留分減殺請求が、遺留分権利者が最終的に最低限取り戻すべき金額を取得する手続であり、最終的には遺言により全財産の相続人となった者が全債務を承継することになること、そして、債権者は遺留分権利者ではなく財産全部を相続した相続人に対して全債務の履行を請求する可能性の方が高いことからも、上記判決の判断は妥当なものと思われます。
長文になってしまい恐縮ですが、興味深く参考になる判例でしたので、本稿にて紹介させて頂きました。「では私の場合はどうなるのかな?」と思われた方は、是非お気軽にご相談ください。
