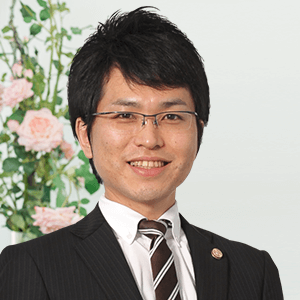こんにちは。本日は親権者の指定に関する裁判例をご紹介したいと思います。
裁判所が親権者を指定する場合、父母のいずれを親権者とするかが子の福祉に適うかという基準から諸事情を総合考慮して判断がなされます。
他の弁護士のブログでも触れられていますが、多くの裁判例においては、親権者の指定の判断基準として、母親優先の基準、継続性の基準、子の意思の尊重の基準、きょうだい不分離の基準などが用いられています。
本日ご紹介する裁判例は、継続性の基準に関する裁判例(東京高裁判決昭和56年5月26日・判時1009号67頁)です。
事案
Ⅹ(夫)とY(妻)には、婚姻後、長男aと二男bが生まれたが、その後、夫婦仲が悪くなり、Yは、長男、二男を残したまま、Ⅹ方を飛び出し、約8か月後にⅩ方に戻った。その翌年、Yは、離婚調停を申し立て、実家に戻った。
その際、長男(当時9歳)はYと同行することを望み、二男(当時5歳)はⅩ方に残ることを望んだため、Yは長男のみを連れて実家に戻った。別居後は、Ⅹが二男を、Yが長男を養育している。
その後、Ⅹは、Yに対して、離婚等を求める訴訟を提起した。
一審は、離婚を認め、長男と二男の親権者をYと定めた。
Ⅹは、一審判決中、親権者の指定部分についてのみ不服申し立てをした。
本判決は、原判決の一部を取り消し、長男の親権者をY、二男の親権者をⅩと指定しました。
理由は以下の通りです。
「本件においては、このように既にⅩとYは完全に別居し、その子を一人ずつ各別に養育するという状態が2年6月も続いており、その間、それぞれ異なる生活環境と監護状況の下で、別居当時、5歳4月であつたbは8歳に近くなって小学校一年生を終えようとしており、9歳になったばかりで小学校三年生であつたaは11歳半となり、やがて五年生を終ろうとしている状況にある。離婚に際して子の親権者を指定する場合、特に低年齢の子の身上監護は一般的には母親に委ねることが適当であることが少なくないし、前記認定のようなⅩの環境は、監護の条件そのものとしては、Yの環境に比し弱点があることは否めないところであるが、Ⅹは前記認定のとおり、昭和五三年八月以降の別居以前にも、Yの不在中、4歳前後のころのbを約8か月間養育したこともあって、現在と同様な条件の下でbと過ごした期間が長く、bもⅩによくなついていることがうかがえる上、aについても、bについても、いずれもその現在の生活環境、監護状況の下において不適応を来たしたり、格別不都合な状況が生じているような形跡は認められないことに照らすと、現在の時点において、それぞれの現状における監護状態を変更することはいずれも適当でないと考えられるから、aの親権者はYと、bの親権者はⅩと定めるのが相当である。」
このように、本判決は、「離婚に際して子の親権者を指定する場合、特に低年齢の子の身上監護は一般的には母親に委ねることが適当であることが少なくない」として、母親優先の基準に言及しつつも、aとbの「監護状態を変更することはいずれも適当でない」ということを理由として、親権者を指定しています。
継続性の基準とは、子供の健全な成長のためには親と子の普段の精神的結びつきが重要であって、養育監護者の変更は子の心理的不安定をもたらすことを理由に、現実に子を養育監護する者が優先されるというものですので(青林書院『離婚調停・離婚訴訟』143頁)、本判決は継続性の基準に拠って親権者を指定しているといえます。
親権者の指定において、母親が有利で父親が不利であることは、他の弁護士のブログでも再三触れられているところですが、上記のように、現実に子の養育監護を継続していることは親権者の指定において、母親優先の基準を覆す有力な事実です。
以上から、親権を獲得するためには、現在、お子さんを養育されている方はその状態を維持することに努め、相手方のもとにお子さんがいるという方は自分のもとでお子さんを養育できるようにすることが、非常に重要であることがご理解いただけると思います。
しかし、相手方のもとにお子さんがいる方が実力行使にでてお子さんを自分のもとに連れてくることは避けねばなりません。子を連れ去った行為に違法性がある場合には、連れ去った者の親権適格に問題があり、連れ去った親のもとで子どもが安定した生活を送るようになっても、それは連れ去りの結果であって追認されない可能性があるからです(東京高裁決定平成11年9月20日・家月52巻2号163頁参照)。
そこで、一般民事手続、家事審判手続、人身保護手続の中から適切な手続きを選択して適法にお子さんを取り戻すことが必要となりますが、そのためには専門的知識が必要となりますので専門家である弁護士にご相談されることをお勧め致します。