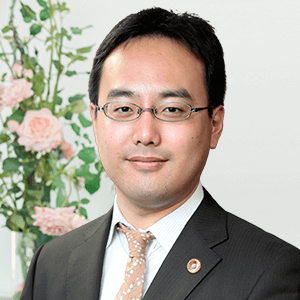前回のブログでも説明したとおり、具体的な事案において、法人格が否認されるか否かを決める明確な基準はありません。
(前回の記事はこちら:法人格否認の法理1)
法人格を否認すべきか否かの判断を分ける基準は、当該事例において法人格の独立を貫くことが正義・衡平に反するか否かという極めて抽象的なものです。
自分が新会社を立ち上げるなどするときに、それが法人格否認の対象とならないかを知るためには、類似の事案を探して、その結論から推測するべきでしょう。
今回から、数回に渡って、法人格否認が問題となりうる場合を個別具体的な裁判例とともに検討していこうと思います。
今回は、法人格否認の法理の適用が問題となる類型のうち、法人格の形骸化について触れます。
前回触れた大阪高裁の判決では、法人格が形骸化している場合を「法人とは名ばかりであって子会社が親会社の営業の一部門にすぎないような場合、すなわち、株式の所有関係、役員派遣、営業財産の所有関係、専属的取引関係などを通じて親会社が子会社を支配し、両者間で業務や財産が継続的に混同され、その事業が実質上同一であると評価できる場合」と述べていました。その他、法人格の形骸化については、「個人企業で会社と株主とが実質的に同一である。」とか、「子会社が親会社の一事業部門にしか過ぎない。」などと表現されることもあります。
裁判例では、前回触れた大阪高裁の判決は、A社がB社の①全株式を保有し、②B社の従業員の労働条件をA社が決定し、③売上を管理し、④重要な資産に関する事項も行っていたことから、A社のB社に対する支配は認めたものの、④財産と収支の混同がなかったことから法人格の形骸化は否定しました。
大阪高裁平成12年7月28日判決は、①主たる活動分野が異なること、②両会社で財産の混同がないこと、③従業員もほぼ別であること、から、法人格の形骸化は否定しました(金融・商事判例1113-35)。
東京地裁昭和55年8月28日判決は、①事務所の場所が同一、②代表者はじめ主要な幹部が共通、③A社がB社から商標使用料や賃料、株式配当金を受領しているなどから、管理支配の関係を認めましたが、④組織、業務内容、財産及び経理関係に混同はなかったとして、法人格の形骸化は否定しました(判例タイムズ425-163)。
このように、法人格の形骸化については、支配性と組織の同一性が主として判断要素となっていると考えられますが、特に同一性が認められないことが多く、なかなか法人格の形骸化に該当するとは認められないようです。