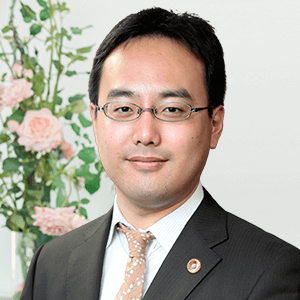不景気の折、新事業を立ち上げて新会社を設立し、グループの経営の軸足を新会社へ移すことで不採算となった既存部門を整理したいと考えることがあるかもしれません。しかし、そのような場合に、グループの資力の整理と集中を気を付けて行わないと、新会社は旧会社と法人格が別であることを利用して財産のみを移転し、旧会社の債務逃れを行ったとみなされる可能性があります。そうなると、法人格が否認されることで、せっかく独立した新会社に旧会社の債務の履行請求をされることになるかもしれません。
法人格否認の法理とは、法人格の独立性を形式的に貫くことが、正義・衡平に反する場合、当該事案において会社の法人格の独立性を否定し、会社とその背後の者を同一視して事案の衡平な解決をはかる法理を言います。
判例上、法人格の独立を否定するべき場合として挙げられるのは、
① 法人格が濫用されている場合
② 法人格が形骸化している場合
です。
①法人格が濫用されている場合について、判例はこの類型に該当するために、支配要件(法人格が支配者により意のままに道具として支配されている)と目的要件(支配者が違法または不当な目的を有している)の両方が認められることを必要としています。
②法人格が形骸化している場合の例としては、大阪高等裁判所が、「法人とは名ばかりであって子会社が親会社の営業の一部門にすぎないような場合、すなわち、株式の所有関係、役員派遣、営業財産の所有関係、専属的取引関係などを通じて親会社が子会社を支配し、両者間で業務や財産が継続的に混同され、その事業が実質上同一であると評価できる場合」を挙げています(労働判例975号50頁)。
法人格が否認されると、その効果として、「会社の活動から生じた権利義務はその会社に帰属し、他の会社(他に株主等)には及ばない」という原則(法人格の独立性)が当該事案限りで否認されます。
法人格否認の可否・要否の判断は、それぞれの事案における個別具体的な事情に基づくところが大きく、明確な一つの判断基準を立てることは難しいものです。判例も、上記のとおり、漠然とした基準しか挙げておらず、参考にするに留まるものです。
しいて何かしら基準を立てるなら、当該事例において法人格の独立を貫くことが正義・衡平に反する結果となるか否か、程度にとどまります。
法人格否認の法理の適用の判断については、類似の事例を捜し、それと比較し、本件において法人格が否認されるかを推測することとなります。
今後、法人格否認が争われた事例を、類型別にみていこうと考えます。