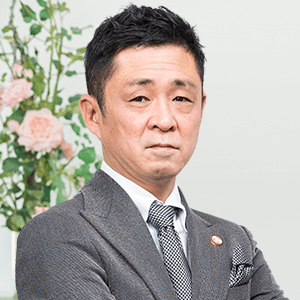1 難しいパワハラ問題
近年、職場におけるパワハラが深刻な問題としてクローズ・アップされるようになりました。同時に“職場のいじめ問題”もクローズ・アップされております。“いじめ”は通常強者から弱者に対してなされるので、これも広い意味でパワハラの部類に属すると思われます。
そして、パワハラ・職場のいじめに関しては裁判例も増加傾向にあります。
しかし、パワハラには、実はセクハラと比べて難しい問題が横たわっています。それは、「何がパワハラに該当するのか」がセクハラ以上に曖昧だからです。この曖昧さはどこから来るのでしょうか。それは、企業が組織である以上、指揮・命令系統を不可欠な要素としている点にあると思われます。
企業は、そもそもパワーを行使する機関です。したがって、企業内におけるパワーの行使の全てがパワハラに該当してしまうと、およそ企業社会は成り立ちませんので、企業内のパワー行使の中には、適法なパワー行使と違法なパワハラがある、ということになります。では、どうような行為が違法なパワハラに該当するのでしょうか?
この点、東京地裁は、損保ジャパン調査サービス事件において、パワハラとは、「組織・上司が職務権限を使って、職務とは関係ない事項あるいは職務上であっても適正な範囲を超えて、部下に対し、有形無形に継続的な圧力を加え、受ける側がそれを精神的に負担と感じるときに成立するもの」と定義しました(東京地裁平成20年10月21日判決)。
この定義の中に、パワハラ概念の難しさが感じられます。例えば、「適正な範囲を超えて」という部分については、どのような行為が適正な範囲を超えたと評価されるのか、その判断は必ずしも容易とは言えません。おそらく、多くの場合、上司は適正な範囲であると考えて権限行使しているはずですから…。「有形・無形に継続的な圧力を加え」という部分も難問です。有形はともかく、無形となると、当然“言葉”も含みます。「圧力」というと、それだけで、何か不当なことをしているような響きがありますが、上司から見るとそれは圧力ではなく「権限行使」だということになります。しかし、この定義だと、上司の言葉による叱責も「無形の圧力」になりかねません。そして、もっとも厄介なのは、「受ける側がそれを精神的に負担と感じるとき」という部分です。最終的にパワハラに該当するかどうかは、それを受ける側の感じ方次第と言っているようなものですから…。
2 パワハラの裁判例
実際の裁判例を見てみると、パワハラで提訴されるようなケースは、その被害を被った従業員がうつ病になったり、自殺してしまったようなケースが多いという印象を受けます。
有名な判例としては日研化学事件がありますが、裁判所は、上司のパワハラが原因による職員の自殺を労災と認めました(東京地裁平成19年10月15日判決)。この事件では、「お前は会社を食い物にしている。給料泥棒だ」、「存在が目障りだ。お願いだから消えてくれ」、「車のガソリン代がもったいない」、「どこへ飛ばされようと、俺はお前が仕事をしないやつだと言いふらしてやる」などという上司の暴言が認定されています。ちなみに、中部電力事件(名古屋高裁平成19年10月31日判決)、川崎市水道局事件(横浜地裁川崎支部平成14年6月27日判決)も、やはり職場のパワハラやいじめが原因で職員がうつ病に罹患し自殺したケースです。
これらはパワハラ被害を受けたとされる職員が自殺までしている極端なケースですが、配点命令等の人事権行使がパワハラだとされた事案もあります(神戸地裁平成16年8月31日判決)。ただ、この事件では、会社側が職員に対して退職勧奨をしたところ、当該職員がそれに応じなかったことが背景としてあります。なので、この裁判では、真に必要な人事権行使ではなく、退職に追い込むための手段として濫用された人事権の行使と評価されてしまっています。でも、これってけっこう微妙な問題ですよね。退職勧奨を伴わない通常の人事異動のほかに、退職勧奨に従わなかったので人事異動を命じる場合の全てが人事権の濫用とは言えないと思います。退職勧奨がなされるのは、その職員の能力面とかやる気とかに問題があって、現状のポストに置いておけないから、というケースも少なくありません。そこで、退職してくれない以上他部署に異動させるしかないわけですが、その場合の異動先は、従来の配属先よりも魅力がない部署になることが多いと思います。重要な任務を任せても「使えない」という判断を会社がしているわけですから…。
3 パワハラに対する社内的取り組み
職員やその遺族から提訴されるリスクだけを念頭に置けば会社のパワハラ対策として十分なわけではありません。
前述したように、パワハラ概念の曖昧さは、職員による“パワハラ主張の濫用”の余地も残すからです。特に、前記東京地裁のパワハラの定義にもあったように、「受ける側がそれを精神的に負担と感じるとき」にパワハラが成立するとなると、上司の権限行使が気に入らない職員は、何でもかんでも“パワハラ”だと強弁することを許してしまいます。
例えば、セクハラが大きな社会問題になったとき、多くの大企業がコンプライアンスの一環としてセクハラ防止対策のガイドラインを策定し、企業内に浸透させるということをやりました。これはこれで立派な姿勢だと思います。そして、パワハラが社会問題になった今、この仕組みをパワハラにも導入すると、大変です。ある会社では、自称パワハラ被害の訴えが増加し、総務部も対応を迫られる。でも、そのほとんどが上司の指示が気に入らないという職員の不満にすぎなかったということでした。そればかりが、職員によるパワハラ被害の訴えが恐くて、逆に上司のほうが萎縮してしまうなどという笑えない報告もあります。当たり前ですが、全ての職員が違法なパワハラに当たるかどうかの法的判断をできるわけではありませんから、ようは自分が不快に思えば全てパワハラなんです。会社が誠実な対応を行えば行うほど、くだらない苦情の処理に追われ、担当部署は非生産的な業務に忙殺されることになります。
それが面倒だからといって社内で何らの対策も講じなかったら、それこそ何か問題が発生したときに、コンプライアンス経営を怠っていたなどという誹りを免れません。
そこで、このような問題の解決策のひとつとして、法律事務所などの専門家機関にパワハラ苦情処理窓口を全てアウトソーシングしてしまう方法があります。この方法の第1のメリットは、セクハラやパワハラの苦情処理という非生産的な活動から解放され、本来の会社の業務に専念できる点です。また、第2のメリットとして、専門家である弁護士等が中立的立場から上司と職員の事情聴取を行いますので、当事者の納得感も高いという点を指摘できます。
いずれにしても、企業としては、パワハラの問題は訴訟リスク対策にとどまらず、日頃の業務の中で適切な予防策を講じておかなければならない時代に来ています。