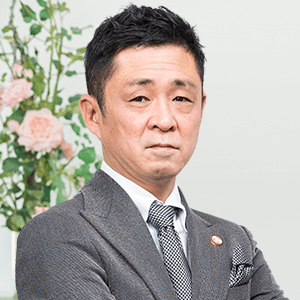1 初めての高裁判決
数ヶ月前に、私がこのブログでも、更新料支払条項を無効とする京都地裁の判決を紹介しましたが、今度は、初の高裁判決です。
判決の論旨に入る前に、そもそも更新料支払条項が「有効」だと主張する立場(賃貸人側の主張です)の整理から解説したほうがわかりやすいかもしれませんね。
賃貸人側の主張は、概ね次のように整理できます。
①更新料は、賃貸人による更新拒絶権放棄の対価としての性格を有する。
②更新料は、賃貸借契約を更新することによって賃借人の賃借権を強化することこに対する対価としての性格を有する。
③更新料は、賃料を補充する性格を有する。
これらの賃貸人の主張に対する大阪高裁の判断は次の通りです。
①賃貸人の自己使用の必要性は乏しい。
②通常は賃貸人からの解約申し入れの正当事由は認められない。
③中途解約の場合に、支払った更新料を精算する条項が盛り込まれていない。
として、賃貸人の主張を退けています。
さらに、大阪高裁は、消費者契約法10条を根拠に、
④更新料支払条項は、「消費者の利益を一方的に害するもの」として無効
と判断しました。
2 賃貸人の各主張について
まず、①更新料は、更新拒絶権放棄の対価であるという主張について。
そもそも、賃貸人の更新拒絶が正当であるというためには、自己使用の必要性が認められなければなりません。しかし、賃貸物件において、賃貸人自らが自己使用しなければならないケースは希です。そうすると、原則として、そもそも賃貸人は更新を拒絶できないわけですから、更新拒絶権放棄の対価を請求するのは筋違いということになります。
②賃借権強化の対価という主張について。
この主張が成り立つためには、その前提として賃貸借契約の更新を重ねるたびに、賃借権が強化されて、その結果、賃借人の保護が強まるという関係がなければなりません。しかし、そもそも、賃貸人に正当事由がなければ、更新を拒絶することはできないわけですから、更新を待つまでもなく、賃借権は強いんですね。しかも、賃貸人の側に正当事由が認められるケースは希です。そうすると、そもそも賃借権は、更新料を支払うまでもなく強いわけですから、賃借権強化の対価という主張には理由がないことになります。
③更新料は、賃料の補充であるという主張について。
この点に関しては、裁判所が鋭い指摘をしています。もし、更新料に賃料を補充する性格があるというのであれば、中途解約の場合、未経過期間分を精算する規定を置くべきであるのに、そのような条項がないことを裁判所は指摘しています。例えば、本当に更新料が賃料の補充的性格を有しているのであれば、例えば、契約期間2年間で、1ヶ月相当の更新料を支払っている場合で、賃借人が中途解約して更新後1年で退去する場合、更新料の半分は返さないといけないことになりますよね。2年を予定して更新したけど実際には1年しか住まなかったわけですから。しかし、そのような精算を行う条項もないし、また、精算をしているという実態もないわけです。このような現実を前にして、賃料の補充という賃貸人の主張に与することはできないと思います。
3 関西以外にも飛び火するか
前述のように、賃貸人側の主張は、法律論としてけっこう苦しい理屈になっています。
だから、なかなか裁判所を説得できないことになります。
更新料の支払いが商慣習化していたというのが真実に近いんでしょうね。なのに、後付でもっともらしい理屈をつけて説明しようとするから、説得力がなくなってしまうわけです。
さて、以前にもブログで書きましたが、更新料支払いの実態は、地域によってかなり差があるという事実が浮き彫りになっています。東京では、多くのケースで更新料が支払われておりますが、大阪・京都などの関西圏では、更新料を請求しない賃貸人もけっこういるそうなんですよ。意外でしたね。関西のほうがしっかり取っているというイメージでした(笑)。
なので、この手の紛争が東京ではなく、関西で起こった背景もその辺にあるかもしれません。東京で生活している人に比べて、関西の人たちのほうが納得していないんですね。更新料の支払いに関して。
でも、このような高裁判例が出たことにより、更新料支払いが半ば慣習化している東京・関東エリアにも飛び火する可能性はあります。
東京で生活している人たちだって、払わずにすむのであれば、払いたくないと思いますから。
また、東京では慣習化しているから、大阪高裁とは異なる判決が出されるはずだと即断するのは危険です。大阪高裁は、関西圏で更新料が慣習化していないから、という理由で賃貸人の主張を退けたわけではないんです。
仮に東京で慣習化していたとしても、それは消費者契約法ができるまでの話。消費者契約法のような法律がなかった時代だからこそまかり通った悪しき慣習だ、という主張も成り立つからです。消費者契約法の射程範囲が、同法制定前の慣習には及ばないと考えるのも問題です。
消費者契約法がある今の時代にあっては、たとえ東京等一部の地域で慣習化している事実があるとしても、消費者契約法の趣旨が優先するという解釈論を裁判所が展開する可能性は十分にあります。