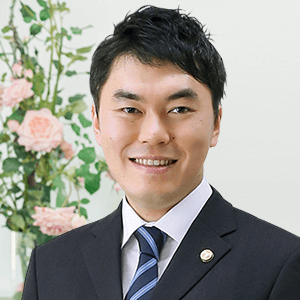1、自白法則
前述の通り、自白はその証拠価値の高さから捜査機関が何としても手に入れたい証拠の一つとなっています。しかし、何としても手に入れたいがために、まだ犯人かどうかもわからない相手に怒鳴りつける、脅迫する、話すまで家に返さない等の違法捜査が数多く行われてきた時代がありました。
このような時代の反省により、現代では刑事裁判における自白の取扱いを刑事訴訟法319条で定めており、これを自白法則と呼んでいます。
*自白の取扱いについては、補強法則という原則もありますが、本稿では説明を割愛します。
(1)法律上の規定
刑事訴訟法319条第1項では、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と定めており、これを自白法則といいます。
このような任意にされたものでない疑のある自白(裁判では、警察官や検察官が被疑者の自白を調書という書面にまとめて提出されることが多いです)は、裁判では証拠として使えなくなるため、これによって捜査機関には無理な自白の引出しを躊躇させる効果が生じるのです。
(2)任意性のない自白の範囲
では、どのような状況での自白が「任意にされたものでない疑のある自白」になるのでしょうか。これについては、そもそも自白法則が何のためにあるのか、という根拠に遡って考えなければならず、その根拠も複数の考え方があって今でも完全な結論は出ていない状態です。これらを全て話したのではとても紙面が足りませんので、ここでは裁判所の考え方をいくつか紹介します。
裁判所では、任意性の無い自白をとても広く解釈しており、条文で例示しているような脅迫や長期の取調べによる自白はもちろんの事、利益誘導(素直に話せば起訴しない、処分が軽くなる等の甘言を囁くこと)による自白(最判昭和41年7月1日)、切り違え尋問(共犯者ABに対し、Aには「Bが自白した」と言い、Bには「Aが自白した」と言う取調べ方法)による自白(最大判昭和45年11月25日)、物的証拠が出たと嘘を言って被疑者を観念させて得た自白(東京地判昭和62年12月16日)等についても自白の任意性を否定しています。
ですから、脅されたか騙されたかに関わらず、警察や検察に不当に影響された状態でした自白については、ほとんどが任意性の無い自白として争うべきといえるでしょう。