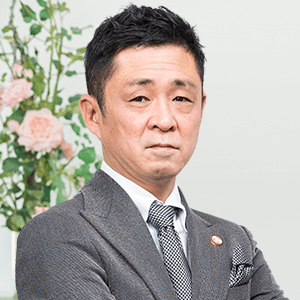前回の記事はこちら:不動産投資入門3(区分所有法)
4.投資利回りに影響を与える法律関係
(1) 賃料
不動産投資の利回りの中核をなすのは、言うまでもなく賃料です。
賃料については、1つだけ法律的に重要なことがあります。それは、合意した賃料は絶対的なものではないということです。
本来、私的自治の原則[12]からすれば、合意した内容に契約当事者は拘束されることになります。したがって、当事者間で設定された賃料が、近隣の相場と比較して割安であろうと割高であろうと、当事者は合意した賃料の額に拘束されるのが原則です。
しかしながら、賃料が①土地または建物に対する租税等の負担の増減した場合、②土地または建物の価格の上昇・低下その他の経済的事情が変化した場合、③近隣の同種の建物の賃料と比較して当該賃料が不相当となった場合、当事者は、将来に向かって賃料の額の増減を請求できます(借地借家法第32条)。
この制度は、固定資産税が上がったり、経済事情の変化により賃料相場が上がった場合等には、賃貸人が賃借人に対して、賃料の増額を請求することができることになるのですが、逆に賃借人から賃料の減額を請求される場合もありうるということです。
賃料の増減について、当事者間で協議が整わなかった場合、訴訟をすることになりますが、その場合には裁判所が適切な賃料を決めてくれます。ただ、賃料の増減額の請求を訴訟で実現しようとすると、かなり骨の折れる作業になります。いくらが適正な賃料かということは、本来は法律問題ではありません。そこで、通常は、不動産鑑定士などの専門家にお願いして、適正な賃料に関する意見について鑑定書を作成してもらい、それを裁判資料に用います。このような事情に鑑みると、けっこう裁判にかかる費用もバカにならないというのが実情です。
(2) 敷金・礼金
分譲マンションを賃貸すると、賃貸人は敷金と礼金を賃借人から受領することができるというのが半ば商慣習のようになっております。東京では礼金不要とする賃貸物件が増加しておりますが、地方ではまだまだ健在のようです。
しかし、この敷金と礼金は、法律的にはかなり性格を異にするものですので、その違いをしっかり理解することが必要です。
まず、礼金は、基本的に賃借人に返還する必要がない金員ですので、投資利回りに貢献すると考えてよいでしょう。ただし、礼金は契約時に1回だけ支払われるものですから、投資利回りに対する貢献といっても些細な程度にとどまります。
ところで、礼金は、その法的性質が判然とせず、賃借人の立場からすると、これを支払わされる根拠が明確ではありません。近時、更新料の無効判決がマスコミなどでも話題になっていますが、礼金も似たような問題を内包しています。結局、賃借人の弱みにつけ込んで不当に徴収している金員だと見られる余地があるからです。現在のところ、礼金の有効性が争われた裁判は見受けられませんが、更新料無効判決を受けて、礼金に飛び火する可能性があるので注意が必要です。
次に、敷金は、賃借人が賃貸物件を毀損するなどして賃貸人に損害を与えた場合の担保として徴収されるものですから、賃貸借契約が終了した後、精算して賃借人に返還しなければなりません。ということは、賃料や礼金のように賃貸人の収益にするわけにはいきませんので、基本的に投資利回りに貢献するものではないと考えるべきです。もっとも、敷金と言えども、返還するまで金庫にしまっておかなければならないわけではなく、返還するまでの間、他に運用することが可能ですから、厳密に言えば、投資利回りに全く貢献しないとまでは言えないかもしれません。
ところで、敷金返還請求権はいつ生じるのかについて、①賃貸借契約終了時に発生するという考え方と、②建物明渡時に発生するという2つの考え方がありますが、①の考え方だと、賃貸借契約終了後、明渡前までに生じた損害に対して、敷金が担保として機能しなくなってしまうという問題が生じます。そこで、今日の判例は②の考え方を採用しています[13]。したがって、賃貸借契約終了時に賃借人に敷金を返還する必要はなく、建物明渡後、合理的な期間内で精算して返還すれば足ります。
[12] 私的自治の原則が働く結果、当事者の合意した内容が強行法規や公序良俗(民法第90条)に違反しない限り、当事者の合意が法律に優先することになる。なお、内田貴著「民法Ⅰ〔第4版〕総則・物権総論」35頁参照。
[13] 最高裁判決昭和49年9月2日。同判決は、敷金が賃貸借契約終了後明渡しまでの損害金についても担保するから、明渡しの時点で初めてその額が確定することを根拠としている。