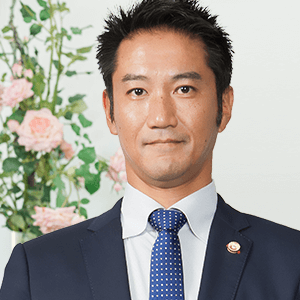遺言は厳格に方式が法定されており、その方式を守っていなければ、基本的には無効と判断されてしまうことはご存知だと思います。これは、遺言の効力の発生が遺言者の死亡時であるため、遺言が効力を生じた時にはその意思を確認できないことから、なるべく疑いが生じないようにすることが理由とされています。
他方で、遺言は、そもそも、死亡時に自分の遺産をどう処分するかについて、その意思を尊重しようとする制度ですので、できるだけ遺言者の意思を汲むべきとの要請があります。
少しでも方式が間違っていれば全て無効としてしまうとすると、遺言者の意思を置き去りにしかねませんし、方式を緩やかに解釈しすぎても遺言者の意思に反した遺言が生まれてしまうことにもなります。
そこで、実務上は、遺言の方式が要求される実質的な意義や趣旨に反しない範囲で、比較的柔軟に解釈されているのが実情です。
例えば、自筆証書遺言には、遺言の内容となる全文、日付、氏名の全てを自書したうえで、押印することが求められていますが、日本で長年生活していたものの、主としてロシア語と英語を使用しており、生活様式もヨーロッパ様式に従い、交際相手もほとんどがヨーロッパ人であったロシア人男性が、帰化後しばらくして自筆証書遺言を作成したものの押印をしなかったという事案で、裁判所は、遺言を有効と判断しています(最高裁判所判決平成49年12月24日民事判例集28巻10号2152頁)。
また、遺言書自体には押印をしていなかったものの、遺言書の封書の封じ目に押印がされていたという事案において、有効だと判断したものがあります。
厳密に考えれば、遺言書に押印がなかったのですから、各遺言は無効なはずですが、具体的事情を踏まえて、押印を要求した異議に反しない範囲で有効と判断したものです。