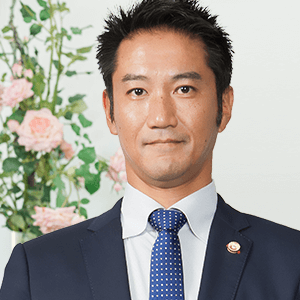Ⅰ 事案の概要
東京都(都)の1年任期の専務的非常勤職員である消費生活相談員(本件相談員、任期1年)を組合員にもつ労働組合(本件組合)は、東京都が専務的非常勤職員の雇用期間の更新回数を原則4回までとした(本件要綱改正)ことや次年度の勤務条件等について、団体交渉(団交)を申し入れたが、都がこれに対して雇用関係終了後の労働条件については団体交渉事項に含まれないことを理由に拒否したところ、東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為救済の申立てを行いました。都労委は、都の対応は、不当労働行為(労働組合法7条2号)に該当するとして、東京都に対し、誠実に団交に応ずるべきことを命じました(本件命令)。都の中央労働委員会に対する再審査申立ても棄却されたため、都がこれを不服として国に対し、本件命令の取消を求めました。
第1審東京地裁が、都は労働組合法(労組法)7条2号にいう「使用者」にあたり(争点①)、本件要綱改正及び本件相談員の次年度の勤務条件は、義務的団交事項にあたる(争点②)として、都の請求を棄却したため、都が控訴したところ、控訴も棄却されました。なお、都が上告及び上告受理申立をしたものの、それぞれ棄却及び却下されました(最決平成26年2月7日)。
Ⅱ 判決の要旨
本件相談員に対しても労組法が適用されることを前提としたうえで、労組法7条2項によると、使用者は、正当な団交申入れを拒むことはできないことから、以下の2点が争点となりました。
(1)労組法7条2号「使用者」該当性(争点①)
裁判所は、
「労組法7条にいう「使用者」は、労働契約関係ないしはそれに隣接又は近似する関係を基盤として成立する団体労使関係上の一方当事者で賃金を支払う者を意味し、その一方当事者と特定の労働者との間の労働契約が法律上終了することが予定されているとしても、直ちに再び当該労働者との間に従前と同様な労働契約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存する場合には、上記一方当事者は、当該労働者との関係で労組法7条にいう「使用者」に該当するものと解するのが相当である。」
と定義し、本件相談員が更新希望をしながら更新されなかった例はないこと、過去4年間に退職した本件相談員の平均勤続年数は7.5年であること、勤務期間の更新時に都の担当者が本件相談員に対し期待を持たせる発言したこと等を考慮し、
「組合が東京都に団体交渉を申し入れた当時、東京都と本件相談員との間では、1年の任期が経過した後、契約が更新されて新たな労働契約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存在していたということができるから、都は、労働契約関係ないしはそれに隣接又は近似する関係を基盤として成立する団体労使関係上の一方当事者として、本件相談員によって組織される労働組合からの団体交渉申入れに応ずべき労組法7条の使用者に該当していたものというべきである。」
と判示しました。
(2)義務的団交事項該当性(争点②)
専務的非常勤職員の雇用期間が1年(更新可能)であり、これまで本件相談員が更新を希望しながら更新されなかった例はなかったことからすると、本件要綱改正がされた当時、現に任用されている相談員が次年度も引き続き任用される可能性は高く、また、担当部署に少なくとも4名以上の本件相談員が加入しており、次年度に都の任用する相談員の中に本件組合員が存在する可能性も極めて高かったという実態から、次年度の勤務条件は、現に都に任用されている本件相談員の勤務条件であるということができるとし、また、専務的非常勤職員の雇用期間の更新回数を原則4回までに制限する本件要綱の改正も、都との任用関係における本件相談員の待遇の一部に関わるものであるから、本件相談員の勤務条件に重要な変更をもたらすものということができるとしました。
そのうえで、「専務的非常勤職員の次年度の勤務条件及び本件要綱改正は、専務的非常勤職員の勤務条件に関するものとして、義務的団交事項に該当すると解すべきである。」と判示しました。
(3)結論
以上から、裁判所は、都の控訴を棄却し、都は団体交渉に応じることが義務付けられました。
Ⅲ 本裁判例から見る実務における留意事項
団交に応じる義務は、労組法上の労働者と使用者間において認められるものです。自社の労働者と全く無関係な労働組合からの団交の申し入れに応じる義務はないということは当然であるようにも思われます。とすれば、労働契約が終了した後や終了する予定以降の労働条件については、労働者と使用者の関係が失われる以上、団交に応じる義務はないとも思われがちです。しかしながら、複数回にわたり更新を繰り返しているような場合も多くの会社で生じており、事実上、更新が前提とされているような事情がある場合もあります。
本件は、契約更新に関する団交申し入れであったことから、更新するか否かは都の自由だとも考えられ、団交に応じなければならないか悩むところでしょう。しかし、雇止めに関して、契約更新への期待権を保護しようとする裁判例の動向、労働契約法をはじめとする法改正の流れからすれば、慎重に対応すべき事案でした。
様々な理由から契約社員、請負、派遣労働者等の利用が多く行われている中、労働者保護に傾く判決が増加傾向にあること、労働契約法の法改正や労働者派遣法の改正審議などがめまぐるしく進み、労働契約のみなし申込みの制度化が導入され始めていることからすると、このような動向を踏まえた対応が必要となるでしょう。
例えば、派遣社員が加入する合同組合が派遣先に団交を申し入れた事件(神戸地判平成25年5月14日)で、派遣先の使用者性が、採用の自由を理由として否定されましたが、労働者派遣法の改正が施行された場合、採用の自由を理由として同様の判決となるかは不透明なのが良い例だと言えます。
余談ですが、労働組合と言っても個々の個性があり、闘争的な組合もあれば、柔軟な組合もあり、担当者によっても千差万別です。合同労組であれば、寄り合い所帯であることから組合員と組合とに温度差があって団結力が弱い場合も多いものです。事案もさることながら組合の個性も見極めることが重要となります。