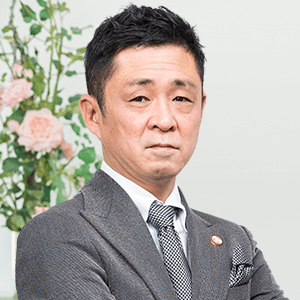顧問先企業の多くが弁護士に不満
先月、幻冬舎から私が書いた新書が出ました。タイトルは「御社の顧問弁護士はなぜ役に立たないのか」です。同業者が聴いたら袋だたきにされそうなタイトルですよね(笑)。同業者からは不評だと思いますが、企業関係者からは好評のようです。「いや~、実に気持ちのいいタイトルですね」というのが営業先企業の担当者の一般的な反応ですから(笑)。多くの企業が弁護士に不満をもっていることが分かります。
そもそもこの本を書こうと思ったのは、旧態依然とした弁護士業界の実態を明らかにしたかったからです。弁護士が一人しか在籍していない法律事務所の数は、日本全国で64.65%に及びます(2009年度版「弁護士白書」)。しかも、複数の弁護士が在籍している法律事務所でさえその約6割が経費節約のためにコストだけを共同で出し合っている「経費共同事務所」ですから、その実質は個人事業主の寄せ集め……(2008年度版「弁護士白書」)。そうすると、実質的には日本全国の約8割が一人で経営する事務所ということになります。
したがって、経営のド素人がたったひとりで何とかまわしているのが法律事務所です。その結果、何が起こるか。事業としての成長戦略が欠如していることはもとより、マーケティング機能がない、商品・サービス設計機能がない、人事制度もなければ業務効率を図ったオペレーション機能もない……。要するに、企業なら通常備えているはずの機能がほとんどないわけです。これでは顧客ニーズを真剣に考える法律事務所なんて皆無に等しくなるのは当然ですよね。
管理不在の杜撰な事務所経営
では、その結果、弁護士の仕事はどのような影響を受けるのでしょうか。そもそも管理能力のない弁護士がたった一人で仕事をこなすので、全ては自分の頭の中……。当然に事件処理は杜撰になるしクライアントへの報告も滞ります。日弁連が毎月発行している「自由と正義」の懲戒処分者一覧を見ると、その懲戒事例の多くは、「弁護士が仕事を放置している間に、クライアントの権利が時効で消滅してしまった」、「弁護士が控訴理由書の提出を忘れている間に、その提出期限が過ぎてしまった」、「仕事をさぼっていた弁護士が、クライアントから報告を求められたため、ちゃんと仕事をしていたという虚偽の報告書を作成した」などという職務怠慢を理由とするものがほとんどです。医療の世界と比べると、私たちの業界はかなり恵まれています。法律家として未熟だったために懲戒される事例がほとんどないわけですから、弁護士としての能力が低くてもとりあえず真面目に仕事さえしていれば懲戒処分されずにすみそうです(笑)。
こういう私にも実際には弁護士ひとりで事務所を運営していた時代がありました。弁護士が私だけだったので、当然法律相談や打合せ、裁判所への出頭、訴状・準備書面などの作成も全て一人で行っていました。外出も多かったため職員の指導・管理も行き届かず、当時の私もお恥ずかしながら杜撰な事件処理をしていた傾向があったことは否めません。ここから分かることは、弁護士がひとりで運営している法律事務所に、“経営”は存在しないということです。独立した弁護士は、自分のことを経営者だと思っている傾向がありますが、これは大きな間違いです。個人で運営しているいわゆる“自営業”には経営は存在しません。この点、日本語の表現は誤解を招くと思います。
自営業は、英語では“self-employment”となります。つまり、自らが自分自身を雇用しているという意味です。言い換えれば、他人に使われていない労働者なんです。
このままではまずいと感じた私は、経営(=management)を法律事務所に導入することを考えました。そのために、稼いだお金を自分の収入にまわさずに“人を雇う”という投資にまわしました。新人弁護士や職員を雇用する資金にまわしたのです。まだ私が八王子市内で法律事務所をやっていた頃の話ですが、初めて勤務弁護士を雇用したとき、その勤務弁護士と私の年俸の差はたったの100万円でした。勤務弁護士の年俸600万円、私の年俸が700万円です。売上は6000万円を超えていたのですが、私の可処分所得にせずに投資にまわしたわけです。雇用ばかりではありません。事務所のIT化を促進するための設備投資も必要です。このように、私は、売上が上がる度に自分の所得を当分据え置いて、どんどん投資にまわして自営業型の法律事務所からの脱皮を図ったわけです。その結果、私は経営(=management)のために頭と労力をさく時間を確保できるようになったんです。現在の弁護士法人ALGの土台となる経営基盤はこうしてできあがったわけです。
弁護士の精神構造
でも、多くのフツーの弁護士にはこれができません。前近代的な経営手法からなかなか脱皮できないんです。
その理由を探るには、一般的な弁護士の精神構造を分析してみる必要があります。私が出した著作の中でもこのテーマを取りあげています。これも同業者が読んだら袋だたきですね(笑)。でも本当の話です。
そもそも弁護士が“経営者”になれないのには、根深い理由があります。それは遡れば、弁護士になろうと思った動機から始まります。
弁護士になりたい人の多くの動機は、“企業が嫌いだから”というところから出発します。要するに、他人から管理されたり他人を管理するのがそもそも嫌い。弁護士が一般的に“自由業”だと言われるのもそこにあります。企業で働くと不自由だが、弁護士になれば自由になれる、というわけです。ということで、法律事務所に企業的な仕組みを導入しようとすると、多くの弁護士はかなりのアレルギー反応を起こします。
問題はこればかりではありません。弁護士が一般的に抱いているエリート意識がそれです。最近は、司法試験の合格枠が大幅に拡大したので、今後、それが世間の弁護士に対するイメージにどのように影響するのかわかりませんが、従来から司法試験は“最難関の国家試験”として位置づけられて来ました。司法試験に合格しただけで、そこそこの評価をいただいてしまいます。なので、この理屈だと、勤務弁護士も弁護士というだけで一定の評価をもらえてしまう。たとえ、企業がそのような評価をしていなかったとしても、エリート意識とプライドの高い弁護士は、弁護士というだけで高い評価をされているはずだという幻想を持っています。これは通常の企業社会ではありえないことですよね。さらに付け加えると、特に男性弁護士の場合、“合コン”を通じてこの弁護士のエリート意識は強化されていきます。今まで全く女性から相手にされなかったのに、司法試験に合格しただけで突然合コンのお誘いが増えるからです(笑)。「もてるようになったのは、司法試験に合格したおかげ!」。これまで女性から見向きもされなかったわけですから、当人には司法試験合格以外に心当たりがないわけです。こうして、司法試験に合格しただけで、弁護士はやっぱりすごいというイメージが、弁護士本人の頭の中に刻み込まれます。
さて、これが先ほどの自由業メンタリティーと結びつくとどうなるのでしょうか……。自由業という大義名分の下で杜撰な事件処理が継続される上に、改善の努力をしようとか、組織化して顧客満足度を高めようとかいう意識は生まれません。弁護士だというだけで偉いわけですから、“偉い人になる努力”なんて必要ないわけです。まさに負の相乗効果ですよね。このような弁護士にとっては、まさに弁護士になることが人生の目的であり、全てとは言わないまでも人生の目標の大半は達成してしまったということになります。これではいつまでたっても弁護士の仕事ぶりが改善されないわけです。どうですか、けっこう根が深いでしょう……。
弁護士を利用する企業としては、このような弁護士の実態をよく理解した上で(もしかすると、もう十分理解されているかもしれませんが、つきあう法律事務所を考える必要があると痛感します。
では、どのような法律事務所とつきあえばいいのか、次号ではその話の続きをしたいと思います。