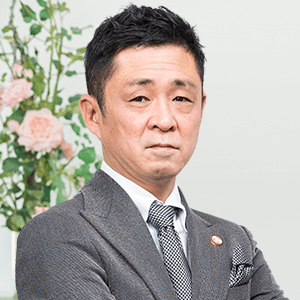1.はじめに
日本も国際物品売買に関する国連条約に批准し、2009年8月1日に発効されることになりました。 そこで、今回は、この条約について、簡単にポイントを指摘しておきたいと思います。
2.加盟状況
まず、現在のところ、加盟国は約70国に及び、多国間条約としては国際社会において定着してきた感じがします。加盟国の中には、日本と関係の深いところでいうと、アメリカと中国も加盟しています。
ちなみに、イギリスは加盟しておりません。こんなことを書くとイギリス人に叱られそうですが、書いちゃいます。イギリスという国はとてもプライドが高いようで、自分たちの国の法律がグローバル・スタンダードであるべきだ、と考えているようです。したがって、英米法とは異なる何とか条約などというわけのわからないものに、自分たちが拘束されるなんて納得できないんですね。あくまでも、私の個人的な分析ですけど……。
3.この条約の一般的注意事項
日本も加盟国となったので、8月1日以降、日本の企業と他の加盟国内に営業所を持つ企業との間での物品売買にこの条約が適用されることになります。 しかし、いくつか注意しておくべきポイントがあります。
① 企業間の物品売買に限られる(2条)
あくまでも企業間の物品売買に限られるので、企業と消費者との間の物品売買には適用がありません。
② 各国の留保条項に注意する
この条約に限らず、多国間条約に一般的に見られる傾向が条約の留保です。条約の中に一部納得できない条項があるために条約の加盟国になれないとすると、多数の国が加盟する条約を結ぶことは極めて困難になります。そこで、多国間条約の世界では、「この条約の中のこの条項はいやだ。それ以外はOK」という具合に、一部の条約の適用を回避する形で加盟国になることができるんです。これを条約の留保といいます。
日本に限らず、アメリカでも中国でも留保条項があります。そして、留保条項は加盟国により異なる場合がありますので、事前に調べる必要があります。
③ 適用排除特約を設けることができる(6条)
この条約の加盟国の企業であっても、売買契約を締結するときに、この条約の適用を排除する特約を結ぶことが認められています。適用の排除は、条約の一部の条項を選んで排除することもできますし、条約全体の適用を排除することもできます。
もし、適用を排除した場合、契約当事者間で準拠法をどこの国の法律にするか、合意しておくのが通常です。その合意をしておかないと、国際私法のルールに基づいて、準拠法が定まることになります。
4.この条約の特徴(特に、日本の民法との違い)
この条約の内容をここで全て解説することはできませんので、特に日本の民法との相違点に着目して、気づいた点をご紹介したいと思います。
① 隔地者間の契約において、日本の民法は、承諾の通知を発した時に成立するとして発信主義を採用していますが(民法526条)、この条約では到達主義を採用しています(18条2項)。
② 日本の民法は、「承諾の期間を定めてした契約の申し込みは撤回することができない」としています(民法521条)。また、「承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申し込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間が経過するまでは、撤回することができない」としています(524条)。
したがって、日本の民法の場合、これらの要件を充たさなければ撤回できないわけですから、撤回は原則として禁止されていると言えます。
これに対して、この条約だと、相手方が承諾の通知を発する前に撤回の通知が相手方に到達すれば撤回ができることになっています(16条)。そうすると、相手が迷っている間に、申し込みを電子メールかFAXで撤回してしまうこともできるようになります。私個人としては、こちらの制度のほうが合理的な気がします。
③ 申し込みと承諾の軽微な相違と契約不成立の回避
例えば、承諾する側が条件を付して承諾すると、申込者が提案した契約内容と食い違いが生じますね。承諾者が一部修正を加えちゃっているからです。
日本の民法だと、申込みと承諾が完全に一致しなければ契約は成立しないことになっています。そして、民法は、このように承諾者が条件を付した場合には、修正された新たな申込みをしたものとみなすことにしました(民法528条)。
しかし、この条約では、その承諾者が付した条件がさほど重要でないのであれば、新たな申込みとせずに契約成立を認めてしまえばいいじゃないか、と考えました。そこで、この条約では、「変更を加えた承諾であっても、申込みの実質的内容を変更しない(したがって、重要でない)場合には、変更を加えた内容で契約が成立するとしました(19条)。
ここはどうですかね。一見合理的なようにも思えますが、実質的内容を変更するものか否かをめぐって紛争になる余地はありますよね。日本の民法のほうが紛争予防力があるのではないでしょうか。
④ 物品の保証期間の定め
日本の民法では、物品の保証期間を定める明文規定はありませんが、この条約では、保証期間を2年としました(39条)。
また、その前提として、買主に検査義務を課しています(38条)。これも日本の民法にはないですね。
⑤ 契約解除の制限
民法は、履行遅滞・履行不能があれば、債務不履行として契約解除できると規定していますが(民法541条、543条)、この条約では「重大な契約違反」に限定して、契約の法的安定性を図ることにしました(49条、64条、23条)。
⑥ 解除における催告の不要
民法では履行遅滞による解除の場合には、催告が必要であると規定されています(民法541条)。これは、いきなり解除するのではなく、相手に履行の機会を与えようと考えたためです。
しかし、この条約では、そもそも履行遅滞しているわけだから、最後通牒はいらないと考えたようです。やはり、日本人が考えた法律と違って割り切りがいいですね。したがって、日本の民法のような解除前の催告の規定がありません。
⑦ 重大な契約違反が予想される場合における、履行期日前解除
この条約では、債務者の重大な契約違反が予想される場合には、履行期日前であっても、契約を解除することが認められています(71条)。
日本ではこのような規定はありませんが、紛争予防機能という点ではどうですかね。重大な契約違反の予想は、いうまでもなく解除する側がするわけですから、紛争のきっかけになりそうですよね。
⑧ 危険負担
日本の民法は、特定物売買では契約成立時に買主に危険が移転するとしていますが(534条)、この条約では、原則として、売主が最初の運送人に物品を交付した時点で危険が移転するとしました(67条)。
国際売買ですから、売主としては運送人に交付して自分の手を離れた以上、責任を免れたいのは当然ですから、まあ合理的なルールだと思います。
それでは、次回は、この条約の実務への影響について書いてみたいと思います。